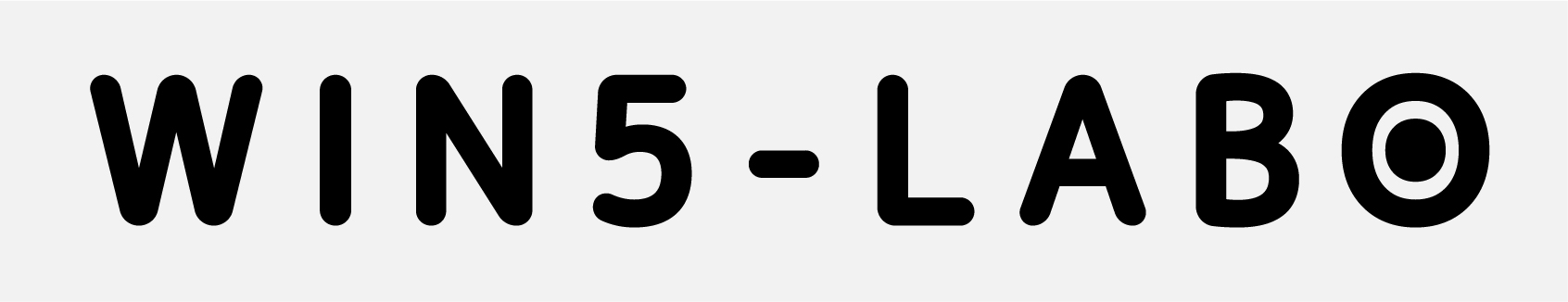競馬の距離カテゴリーの中でも、1400mという距離はどこか独特の響きを持っていますよね。「非根幹距離」とも呼ばれ、純粋なスプリンターでもマイラーでもない、その距離ならではの「スペシャリスト」が存在すると言われます。WIN5においても、この1400m戦がしばしば波乱の鍵を握ることがあると感じませんか?
今回の格言は『1400m戦はその距離のスペシャリストを選ぶべし』です。一見、中途半端にも思えるこの距離だからこそ、特有の適性が求められ、その距離で実績を上げてきた馬、つまり「1400mスペシャリスト」を見抜くことが、WIN5的中に繋がる重要な鍵となるのです。
本記事では、まず1400m戦がなぜ特殊で「スペシャリスト」が存在するのか、その理由を深掘りします。そして、WIN5で実際にあったレースを例に挙げながら、この格言の有効性を解説。この記事を読めば、あなたもWIN5の1400m戦で「スペシャリスト」を見つけ出し、的中への道を切り拓けるはずです。
目次
1400m戦はその距離のスペシャリストを選ぶべし


「1400m戦ではその距離のスペシャリスト馬を選ぶべし」――これが、WIN5で的中を積み重ねる上で僕が密かに重視している格言の一つです。一見、他の距離と大きな違いはないように思えるかもしれません。しかし、この「1000mでも1200mでもなく、マイルでもない」という絶妙な距離設定が、数々のドラマと、そして僕たちWIN5ファンにとっては頭を悩ませる難解さを生み出しています。
ここでは、なぜ1400m戦で「スペシャリスト」を意識することが重要なのか、その核心に迫ります。
この章で解き明かす1400m戦の核心
- なぜ1400mは「魔の距離」?非根幹距離の奥深さ
- 1400mスペシャリスト誕生のメカニズム:適性の正体
- WIN5における格言の真価:1400m巧者を見抜く重要性
なぜ1400mは「魔の距離」?非根幹距離の奥深さ
競馬の距離は、多くの場合400mで割り切れる1200m、1600m、2000m、2400mなどが「根幹距離」と呼ばれ、主要なG1レースの多くがこれらの距離で施行されます。これに対して、1400m、1800m、2200mといった距離は「非根幹距離」と称され、なかでも1400mはその独特の立ち位置から「魔の距離」とも形容されるほど、一筋縄ではいかない奥深さを持っています。
この「非根幹」という言葉、単に「400mで割り切れないから」という以上の意味を、競走馬の能力発揮という観点から含んでいるのです。この1400m戦が「魔の距離」たる所以を、いくつかの側面から紐解いてみましょう。
- スピードとスタミナの絶妙な融合点: 1200m戦のような電光石火のスピードだけでは、最後の200mで脚色が鈍り、ゴール前で交わされるケースが後を絶たない。かといって、1600mを主戦場とするマイラーのスタミナをもってしても、1400m特有の淀みない流れや、時にはスプリント戦並みの追走スピードを要求されると、持ち味である末脚を不発に終わらせてしまうことも。1400mを勝ち切るためには、高いトップスピードを維持しつつ、それをゴールまで持続させるギリギリのスタミナ、そしてレース中のペース変化に瞬時に対応できる器用さが求められるのです。
- ラップ構成の多様性と「息遣い」の難しさ: 根幹距離のレースが、ある程度平均的なラップ(道中の各200mごとのタイム)を刻みやすいのに対し、1400m戦はメンバー構成や展開によってラップ構成が大きく変動しやすいという特徴があります。一部の経験豊富な競馬関係者の間では、「1400mは馬の呼吸のリズム(息遣い)やストライド(一完歩の大きさ)の波長が、1200mとも1600mとも異なる独特のピッチを要求される」と語られることがあります。これは科学的にすべての馬に当てはまるものではないかもしれませんが、馬によっては非常に走りやすい「ゾーン」に入る一方で、多くの馬にとっては最適な呼吸リズムを維持するのが難しく、能力を出し切れずに終わる一因になっている可能性は否定できません。
- 「ごまかし」の効かない真の実力勝負の舞台: 短距離ならばスタートダッシュや展開の利だけで押し切れることもあり、マイルならば多少の位置取りのロスを豊富なスタミナでカバーできる場合もあります。しかし、1400mでは、そのどちらの「ごまかし」も通用しにくいと言われています。スタートからゴールまで高いレベルの集中力と、一瞬の展開変化も見逃さない勝負勘、そしてそれを実行できるだけの操縦性が、人馬共に極限まで試されるのです。
これらの要素が複雑に絡み合い、1400m戦は、その距離に特化した適性を持つ「スペシャリスト」が繰り返し好走する一方で、他の距離では実績十分の人気馬があっけなく凡走するといった波乱も起こりやすい、非常に興味深く、そしてWIN5で高配当を狙う上では見逃せない、攻略しがいのある舞台となっているのです。
1400mスペシャリスト誕生のメカニズム:適性の正体
では、なぜ一部の馬は「1400mスペシャリスト」として、この距離で集中的にその才能を開花させ、他の馬とは一線を画すパフォーマンスを見せるのでしょうか?その背景には、単なる偶然や「器用さ」といった曖昧な言葉では説明しきれない、馬自身の資質と1400mというレース特性との、より深いレベルでの明確な合致が存在します。
「1400mスペシャリスト」が生まれる主なメカニズムとして、以下の点が考えられます。
- 生理機能・心肺機能と「距離の壁」の相関性: 前述の「独特の呼吸リズムやストライドの波長」に、他の馬よりも巧みに適応できる能力を持つ馬がいます。これは、その馬の筋肉の質や心肺機能、エネルギーの燃焼効率が、1400mという距離で求められる「高いスピードの持続力」と「勝負どころでの一瞬の加速力」のバランスに、他のどの距離よりも最適化されていることを示唆しているのかもしれません。あるベテラン調教師は、「マイルではどうしても最後の1ハロンで息が甘くなるが、1200mでは追走で忙しすぎて持ち味の決め手を活かせない。そんな馬にとって、1400mはまさに天職と言える距離なんだ」と語っていたことがあります。これは、その馬の生理的な限界点が、1400mという距離で最高のパフォーマンスを発揮するポイントと合致している、と解釈できます。
- 気性・集中力の最適な発揮フィールド: 競走馬のパフォーマンスは、精神的なコンディションにも大きく左右されます。例えば、レース全体を通して高い集中力を維持できる時間に限りがある馬や、逆にレースに対してなかなか気持ちが乗ってこない、いわゆる「スロースターター」と呼ばれるタイプの一部にとって、1400mという距離と、そこで刻まれやすい平均的なレース展開が、精神的にベストな状態で能力を発揮できる「ゾーン」に入りやすい、という側面があると考えられます。1200mでは短すぎて集中しきる前にレースが終わってしまったり、マイルでは長すぎて途中で集中力が散漫になったり、あるいは道中でリラックスしすぎてしまうような馬が、1400mではまるで水を得た魚のように生き生きとした走りを見せることがあるのは、このためかもしれません。
- 馬体構造と走法(ピッチ/ストライド)の最適解: 例えば、小気味よいピッチ走法(一完歩の歩幅は狭いが、脚の回転が速い走り方)で素早くトップスピード近くまで加速できるものの、大きなストライドで走る馬に比べるとトップスピードの持続力ではやや分が悪い馬。あるいは、ストライドが非常に大きく、一度スピードに乗れば長く良い脚を使えるが、小回りの1200mコースではコーナーリングで不器用さが目立ってしまう馬。こうした特定の馬体構造や走法を持つ馬にとって、1400mのコース形態(例えば、ワンターンで直線もそこそこ長いコースなど)や平均的なレースの流れが、自身の長所を最大限に活かし、短所を補うのに最も適した条件となることがあります。
- 戦術的柔軟性とレースセンスの結晶: 1400m戦は展開のバリエーションが豊富であるため、特定の戦法に固執せず、レースの流れや馬場の状態に応じて自在にポジションを変え、勝負どころで的確に動ける「レースセンス」の高さが求められます。こうした戦術的柔軟性と、それを実行できる騎手との呼吸の合ったコンビネーションも、1400mスペシャリストがコンスタントに結果を出すための重要な要素と言えるでしょう。
これらの身体的、精神的、そして戦術的な適性が複合的に作用し、ある馬にとっては他のどの距離よりも1400mが「自分の庭」となり、その距離で繰り返し好走することで「スペシャリスト」としての評価を不動のものとしていくのです。
WIN5における格言の真価:1400m巧者を見抜く重要性
「1400m戦ではその道のスペシャリスト馬を選ぶべし」という格言。これが、5レース全ての勝ち馬を当てるという至難の業に挑むWIN5において、なぜこれほどまでに重要な意味を持つのでしょうか。その核心は、1400m戦が内包する「波乱の可能性」と、その中で輝きを放つ「伏兵としてのスペシャリスト」を見つけ出すことの戦略的価値にあります。
WIN5でこの格言を重視すべき具体的な根拠を、改めて整理してみましょう。
- 「見えざる適性」が人気と結果を大きく覆す可能性: 1400mという非根幹距離では、他の根幹距離での過去の実績や一般的なクラス評価、あるいは当日の単勝オッズといった、いわゆる「見える情報」だけでは測りきれない、その馬固有の「1400mへの距離適性」が、時に人気や専門家の予想を大きく覆す結果をもたらします。この距離で過去に好走経験がある、あるいは勝利しているという実績は、それだけでこの特殊なレースの流れに対応できる能力を、他の何よりも雄弁に証明していると言えるのです。
- 「人気薄のスペシャリスト」に潜むWIN5的妙味: 他の距離では目立った成績を残せていなくても、1400mという距離に限れば抜群の安定感や勝負強さを発揮する馬が存在します。こうした「隠れた1400mスペシャリスト」は、WIN5においては必ずしも人気上位に支持されるとは限らず、しばしば高配当の立役者となる可能性を秘めています。逆に、他の距離で高い実績を上げてきた馬が、1400m戦ではその適性のなさから過剰に人気を集めて凡走することも。そうした「過剰人気馬」を疑い、見切るための一つの明確な根拠としても、この格言は機能します。
- WIN5における実例が示す「実績」の絶対的な価値: 何も遠い過去の話ではありません。例えば、近年のWIN5対象レースを振り返っても、1400m戦で波乱が起きたケースでは、しばしば1400mという距離で過去に勝利経験のある馬が、人気薄ながらも激走している場面が見受けられます。一方で、そのレースで1番人気に支持された馬が、1400mでの実績に乏しかった、というケースも決して少なくありません。こうした具体的な結果は、机上の空論ではなく、WIN5というシビアな勝負の舞台においても、1400mの「実績」がいかに信頼に足る判断材料であるかを示唆しています。次のH2②では、この点を実際のレースを基にさらに詳しく見ていきましょう。
だからこそ、WIN5で1400m戦の予想に臨む際には、表面的な人気や一般的なクラス評価に安易に流されることなく、出走各馬の「1400mへの適性」と「その距離での過去の実績」を冷静に、そして徹底的に吟味すること。これこそが、難解な1400m戦を攻略し、WIN5的中に大きく近づくための、本質的かつ実践的なアプローチなのです。
(実例検証)1400mスペシャリストが波乱を呼んだ日


「1400m戦ではその距離のスペシャリスト馬を選ぶべし」という格言。その有効性を、僕自身の記憶にも新しい、まさに「特筆すべき」レースとなった2025年5月11日のWIN5対象レースを振り返りながら検証していきましょう。この日、芝1400m戦が2レース組まれていましたが、いずれも1400mという距離への実績と適性が、人気や格付け以上に結果を左右する典型的な例となりました。
この章で深掘りするレース分析
- 橘S:1400m未経験の人気馬はなぜ沈んだのか?
- 谷川岳S:これぞ1400m巧者!実績馬が上位を独占
- 2つの1400m戦がWIN5に与える「実績の重要性」
橘S:1400m未経験の人気馬はなぜ沈んだのか?


まず、京都10レースで行われた3歳オープンの別定戦、橘ステークス(芝1400m外回り)。11頭立てと少頭数で、キャリアの浅い3歳馬同士の戦いということもあり、各馬の能力比較が難しい一戦でした。そんな中、最終的に単勝1番人気に支持されたのは①モンテシート。この馬の戦績を見ると、1600m戦で2勝2着1回3着1回、1200m戦では3着1回と、マイルを中心に好成績を収めており、マイラーとしての資質を感じさせる内容でした。しかし、肝心の1400m戦は今回が初出走。この点がどう出るか注目されましたが、結果は5着と、人気を裏切る形になりました。
一方で、このレースを制したのは、7番人気と伏兵扱いだった③ムイ(今村聖奈騎手騎乗)。この馬は過去に1400m戦で1勝しており、これで1400mは2戦2勝。見事な距離適性を見せつけました。レースぶりを振り返ると、1200mでは少し追走に手間取るというか、エンジンのかかりが遅い印象がありましたが、今回の京都芝1400m外回りという、直線が平坦で広いコース形態がこの馬の瞬発力を最大限に引き出したように見えます。ゴール前の鋭い伸び脚は、まさに「測ったかのような」ハナ差での勝利。この切れ味が、例えば1600mになった時に同じように通用するかは未知数ですが、1400mという距離では抜群の適性を示したと言えるでしょう。
この橘ステークスは、「1400m戦での実績がない1番人気馬が敗れ、同距離での勝利実績がある馬が人気薄ながら勝利した」という、今回の格言を象徴するような結果となりました。
谷川岳S:これぞ1400m巧者!実績馬が上位を独占


では、同日に新潟11レースで行われた4歳以上のリステッド競走、谷川岳ステークス(芝1400m内回り)はどうだったのでしょうか。こちらは橘ステークスとは異なり、古馬混合戦で、コース形態も直線が比較的短い新潟の内回りです。
しかし、ここでも驚くべき結果が待っていました。「偶然」や「たまたま」という言葉で片付けるにはあまりにも出来すぎた話ですが、なんと1着から3着までに入った馬は、このレースに出走した全14頭の中で、1400m戦での勝利数が多かった上位4頭のうちの3頭だったのです。まさに「1400m巧者がワンツースリーを決めた」と言っても過言ではないレースでした。
具体的に見ていくと、このレースで1400m戦での勝利実績が最も多かったのは4勝を挙げていた④ベガリスと⑩スカイロケットの2頭。続いて3勝を挙げていたのが①フルメタルボディーと⑨リミュエールノワルの2頭。他の10頭は、1400m未勝利から2勝馬という状況でした。そして結果は、1着④ベガリス(4番人気)、2着①フルメタルボディー(7番人気)、3着⑨リミュエールノワル(11番人気)という決着。人気上位ではなかったこれらの馬が、揃って上位を占めたのです。
この事実を、単なる偶然として片付けられるでしょうか?ちなみに、このレースで単勝1.7倍と断然の1番人気に支持された②エコロブルームは、G2ニュージーランドトロフィーの勝ち馬で、それまで着外経験がなかった実力馬。しかし、今回は1年ぶりの長期休養明けに加え、1400mは初出走でした(1600m戦2勝、1200m戦3着1回)。レース前の厩舎コメントでは「追い切りの動きはよく、力を出せれば好勝負」と伝えられていましたが、結果は4着。やはり、1400mという距離への実績の壁は厚かった、と言えるのかもしれません。
2つの1400m戦がWIN5に与える「実績の重要性」
同じ日に、異なる競馬場、異なるコース形態(京都外回りと新潟内回り)、そして異なる年齢構成(3歳限定戦と古馬混合戦)で行われた2つの芝1400m戦。これら両レースであえて共通点を探すとすれば、それはやはり「1400mという距離における実績の重要性」が色濃く結果に反映された、という点でしょう。
もちろん、競馬に絶対はありませんし、例外も数多く存在します。僕自身、長い競馬ファン歴の中で、実績のない馬が1400m戦を快勝する場面も見てきました。しかし、それ以上に強く記憶に残っているのは、やはり「この距離ならこの馬だ」と信頼できる、その距離のスペシャリストたちが、その専門性を存分に発揮して勝利を掴む光景です。
特にWIN5という、5レース全ての勝ち馬を当てなければならない馬券においては、一つ一つのレースでいかに「信頼できる軸」を見つけ出すかが重要になります。その点で、この1400m戦における「実績」というファクターは、人気や他の要素に惑わされがちな我々ファンにとって、非常に分かりやすく、かつ頼りになる道標の一つと言えるのではないでしょうか。
1400m戦のスペシャリストを見抜く方法


格言「1400m戦ではその距離のスペシャリスト馬を選ぶべし」をWIN5で実践するためには、単に過去の1400m実績を見るだけでなく、その実績がどのような条件下で生まれたのか、そして今回も同様の能力を発揮できそうかを見極める必要があります。ここでは、1400m戦のスペシャリストを見つけ出す上で注目すべき「馬場」「コース」、そして「血統」の傾向について、具体的なポイントを解説していきます。
この章で探るスペシャリストの鍵
- 馬場状態(芝・ダート)と1400mスペシャリストの相関関係
- コース形態が左右する1400mスペシャリストの得意パターン
- 血統にもヒントあり?1400mスペシャリスト輩出種牡馬
馬場状態(芝・ダート)と1400mスペシャリストの相関関係
1400mという距離は、芝とダートで求められる適性が大きく異なる場合があります。それぞれの馬場でどのようなタイプのスペシャリストが生まれやすいのか、その傾向を見ていきましょう。
- 芝1400mのスペシャリスト:
- スピードの持続力と瞬発力のバランス型: マイルほどのスタミナは要求されないものの、スプリント戦のようなスピードだけでは押し切れないため、高いトップスピードをある程度維持しつつ、最後にしっかり伸びる脚を使える馬が活躍しやすい傾向にあります。
- 高速決着への対応力: 近年の日本の芝コースは高速化が進んでおり、1400m戦も速い時計での決着が多く見られます。軽い馬場を得意とし、スピード能力に秀でたタイプがスペシャリストとして台頭しやすいと言えるでしょう。
- 馬場状態への感度: パンパンの良馬場を得意とするスピードタイプもいれば、稍重~重馬場など、少し時計のかかる馬場での持久力勝負で真価を発揮する馬もいます。馬場状態と過去の好走歴を照らし合わせることが重要です。
- ダート1400mのスペシャリスト:
- パワーと先行力: ダート戦全般に言えることですが、特に1400mでは、砂を被らずに自分のリズムで先行できるパワーとスピードが重要になります。揉まれ弱い馬や、後方から大外を回す競馬ではロスが大きくなりがちです。
- ワンターンコースへの適性: 多くの競馬場のダート1400mはワンターン(コーナーが1回)であり、テンのスピードとコーナーワークの巧さ、そして最後の直線での粘り強さが求められます。このコース形態に特化した馬がスペシャリストとなりやすいです。
- 砂質の影響: 脚抜きの良い軽いダート(例:東京)と、力のいる重いダート(例:中山、阪神)では、好走する馬のタイプが異なることがあります。馬場状態だけでなく、競馬場ごとの砂質の特徴も考慮に入れると良いでしょう。
このように、同じ1400mでも芝とダートでは求められる能力が異なります。それぞれの馬場における「スペシャリスト」の特性を理解することが、的確な予想への第一歩となります。
コース形態が左右する1400mスペシャリストの得意パターン
1400m戦のスペシャリストを見抜く上で、各競馬場のコース形態を理解することは不可欠です。同じ1400mでも、直線の長さ、坂の有無、コーナーの角度や数によって、有利になる脚質や求められる能力が大きく変わってきます。
ここでは、前章の実例検証でも触れた京都・新潟を中心に、主要競馬場の芝1400mコースの特徴と、そこで好走しやすいスペシャリストのタイプを見ていきましょう。
- 京都芝1400m(外回り):
- 特徴: 3コーナーから下り坂が続き、直線は平坦で約400m。スピードの持続力と瞬発力が問われます。
- スペシャリストのタイプ: 下り坂を利用してスムーズに加速でき、直線でのトップスピード能力が高い馬。橘Sのムイのように、決め手のある馬が力を発揮しやすいコースです。
- 新潟芝1400m(内回り):
- 特徴: ワンターンで最後の直線は約360mと比較的短く、平坦。器用さとある程度の先行力が求められます。
- スペシャリストのタイプ: ロスなく立ち回れる内枠の馬や、好位から抜け出せるレースセンスのある馬。谷川岳Sのように、前々で流れに乗れる馬が有利になることも。
- 東京芝1400m:
- 特徴: スタート後すぐにコーナーがあり、直線は約525mと長く、緩やかな上り坂がある。スタミナと瞬発力の双方を高いレベルで要求されるタフなコースです。
- スペシャリストのタイプ: 持久力があり、長い直線を最後までしっかり伸びきれる馬。マイル実績のある馬が好走しやすい傾向も見られます。
- 阪神芝1400m(内回り):
- 特徴: コーナー2つの内回りコースで、ゴール前に急坂がある。パワーと器用さ、そして坂をこなす底力が問われます。
- スペシャリストのタイプ: 好位で流れに乗り、坂も苦にしないパワータイプの馬。瞬発力だけでは押し切れないことが多いです。
- 中京芝1400m:
- 特徴:スタートから最初のコーナーまで距離があり、その後は緩やかなカーブが続き、最後の直線には急坂が待ち構えています。タフな流れになりやすく、総合力が問われます。
- スペシャリストのタイプ:先行力があり、坂もこなせるパワーとスタミナを兼ね備えた馬。器用さも求められるコースです。
これらのコース特性を頭に入れ、各馬の過去のレース内容と照らし合わせることで、その馬が今回のコースで「スペシャリスト」として能力を発揮できるかどうかを見極める精度が高まります。
血統にもヒントあり?1400mスペシャリスト輩出種牡馬
1400mという特殊な距離で輝きを放つスペシャリストたち。その背景には、もちろん個々の馬の能力や気性、成長過程がありますが、「血統」という要素も無視できません。特定の種牡馬の産駒が、1400mという距離で集中的に好成績を収めるケースは実際に存在します。ここでは、1400mスペシャリストを見つけ出す上で、注目しておきたい血統的傾向について触れておきましょう。
1400mという距離に適性を示す血統には、以下のようなパターンが見られることがあります。
- マイル実績馬の父×スプリント実績馬の母(またはその逆):
- 父からマイルをこなせる程度のスタミナと底力を、母からスプリント的なスピードや機動力を受け継ぐことで、1400mという距離で両者の良さが絶妙に噛み合うことがあります。
- 特定の種牡馬系統の得意距離:
- 例えば、かつての名種牡馬の中には、産駒が特定の距離、特にこの1400m前後で抜群の成績を残す、いわゆる「ニックス(相性の良い組み合わせ)」のような傾向が見られることがありました。現代の種牡馬についても、産駒の距離別成績をチェックすることで、1400mを得意とするサイアーラインが見えてくるかもしれません。(具体的な種牡馬名を挙げるのはデータ更新の観点から難しいですが、読者自身がデータを確認するきっかけになるはずです)
- 仕上がりの早さとスピード能力を伝える血統:
- 特に2歳、3歳早い時期の1400m戦では、早期から完成度が高く、スピード能力に秀でた血統背景を持つ馬が活躍しやすい傾向があります。POGなどでも注目されるような、仕上がりの早い血統はチェックしておいて損はありません。
- 馬場適性(芝・ダート)を伝える血統:
- 芝の1400mを得意とする血統、ダートの1400mを得意とする血統もそれぞれ存在します。馬場状態と合わせて、その馬の父や母父がどちらの馬場を得意としていたかを確認するのも有効な手段です。
もちろん、血統だけで全てが決まるわけではありませんが、1400mという特殊な距離だからこそ、血統背景に隠された適性のヒントを探ることは、スペシャリストを見つけ出す上で非常に興味深いアプローチと言えるでしょう。
まとめ:1400m戦をスペシャリスト分析で得意科目に


ここまで、「1400m戦ではその距離のスペシャリスト馬を選ぶべし」という格言を軸に、1400m戦の特殊性、実例分析、そしてスペシャリストを見抜くための傾向と対策について解説してきました。難解と言われる1400m戦ですが、ポイントを押さえれば、WIN5的中の確かな武器になり得るのです。
最後に、WIN5で1400m戦の予想に臨む際に、ぜひ確認していただきたいポイントをまとめます。
WIN5で1400m戦を攻略するための最終チェックポイント
- 「1400m実績」の徹底確認: 最も重要なのは、その馬が過去に1400m戦で勝利、あるいは好走した経験があるか。特に勝利経験は重視すべきです。
- コース適性の吟味: 同じ1400mでも競馬場や内回り・外回りで求められる適性は異なります。出走馬の得意なコース形態と合致しているか確認しましょう。
- 馬場状態(芝・ダート)の考慮: 芝巧者かダート巧者か、そして道悪への適性なども、その馬の過去の戦績から読み解きましょう。
- 展開と脚質の予測: その日のメンバー構成から、どのようなペースになりそうか、そしてどの脚質が有利になりそうか、ある程度の予測を立てておくことが大切です。
- 血統的背景のチェック(補足的に): もし迷った場合は、1400mに適性のありそうな血統背景を持つ馬に注目するのも一つの手です。
- 人気とオッズの盲点を突く: 他の距離での実績で過剰に人気している馬よりも、1400m実績がありながら評価が低い「隠れスペシャリスト」に妙味があります。
1400m戦は、その独特な距離設定から「紛れ」が起きやすく、高配当も期待できる一方で、しっかりと対策を練れば安定して的中を狙える可能性も秘めています。今回の格言と解説が、WIN5-LABO読者の皆様にとって、これまで苦手意識があったかもしれない1400m戦を「得意科目」へと変えるための一助となり、WIN5的中の喜びをより多く味わえるようになることを心から願っています。
『1400m戦はその距離のスペシャリストを選ぶべし』――この格言を胸に、次回のWIN5に挑んでみてください!